「神の■■」
これは、ほんの数週間前の話だ。あれが現実の出来事だったのか、俺には今でもわからない。でも、俺は、行方不明になったはずの少年と山に棲むナニカに出会った、夏の一幕について、ここに記そうと思う。
俺は、大学進学に合わせて上京したばかりの大学一年生だ。前期の授業が終わり、課題も一通り提出し終えて、故郷へと帰ってきていたときに、それは起こった。
俺の故郷は、東京から新幹線で一、二時間のところにある小さな田舎町だ。山の麓に位置していて、水田があたり一面に広がっている。実家を出てから三ヶ月ほどしか経っていないはずなのに、目に映る全てがひどく懐かしい。目にした故郷の長閑な風景に、俺はほっと息を吐いていた。
帰省している間、俺は、高校までの友人と遊びに行ったり、親の庭仕事の手伝いをしたりしていた。親戚の集まりに顔を出すこともあったが、高校はどうだ、という質問が、大学はどうだ、に変わったくらいで、高校生までの夏休みと特に何も変わらずに、日々は流れていく。
何もすることのない時間は、結構あった。そういうときは、俺は一人で山に行く。俺は元々、自然が好きだった。幼い頃から絵本よりも図鑑が好きで、大学では生物を専攻している。
自然への興味はいつまでも尽きることはない。けれど、上京してから、生活の中で自然に触れ合う機会はかなり減ってしまっていた。大学とアパートの行き帰りでは、限られた種類の植物や昆虫しか目にできない。高校生までは、通学路を歩いているだけでも様々な植物や昆虫に出会えたのに、と思うことが多々あった。
だから、俺は、その喪失を埋めるべく、帰省している間、時間を見つけては、山へと足を運んでいた。あの奇妙な出来事の起こった日も、俺はいつも通りに、一人で山に行っていたのだ。
あの日の午前中は、至って平凡だった。取り立てて特別なことは何もない。朝食を摂り、庭仕事の手伝いをし、昼食を食べる。それだけだった。
午後になり、俺は徒歩で山の方へと向かった。山麓に辿り着き、青々とした里山を見上げる。降り注ぐ太陽の光が眩しくて、思わず目を細めた。
俺は、きょろきょろと周囲を見渡した。人がいないことを確認し、山へと足を踏み入れる。幼い頃からの癖だった。
町の子供たちは、子供だけで山に立ち入ることは禁止されていた。山には熊や猪が生息しているし、遭難の危険もある。大人たちの心配は当然のものだった。
けれど、俺は納得できなくて、こっそりと山に入り込んでいたのだ。小学生の頃は、友人何人かと忍び込んでいたが、中学生にもなると、一人で行くことが多くなっていた。その頃には、山の危険性を理解していたが、それを止めようとはしない。代わりに知識を付けて、自らの身を守るように努めていた。
高校生になると、俺は一人で山に行くことを許された。大人たちは、俺の行動に気が付いて、黙認していたらしい。危険は自分で回避できるだろうということで、正式に許可を貰ったのだ。
けれど、隠れずに済むようになっても、つい、周囲を確かめてしまう。小中学校の九年間で身に付いた習慣は、なかなか抜けなかった。
俺は、辺りを観察しながら山道を進んだ。目的地はない。山を歩くこと自体が目的だった。樹木に手を触れて、息を大きく吸い込む。地面に屈み込んで、足元の草花やそこに集う昆虫を眺める。自然に囲まれながら、俺は一人浮かれていた。
俺がそれを目にしたのは、傾斜の厳しい斜面を登っているときのことだ。進行方向に視線を向けながら、力強く地面を踏み締める。坂の半ばに差し掛かったところで、白い何かがひらりと視界の端に掠めた。野生動物だろうか。足音がしなかった。
俺は刺激しないように注意しながら、静かに視線をそちらに向ける。そこにいたのは、白い着物を身に纏った少年だった。
「黒子?」
そんなはずはないと思いながら、俺は呆然と呟いた。足元が疎かになり、転びそうになる。近くの木にしがみ付き、どうにか身体を支えた。
黒子テツヤ。それは、俺の小中学校の同級生の名前だった。特別、仲が良かったわけではない。七年間、同じ学校に通っていたから、会話をしたことは何度もある。同じ町内に住んでいたから、その姿を見かけることも多かった。しかし、放課後に一緒に遊んだことはほとんどない。その程度の繋がりの同級生だった。
俺が黒子について知っていることは多くない。読書が好きなこと。異様に影が薄いこと。物静かだが、意外とノリが良いこと。俺と同じように、一人でこっそり、山に入っていたこと。そして、中学二年生の夏に行方不明になったこと。俺が知っているのは、それくらいだった。
俺は、黒子が山に入っていたことを誰にも伝えなかった。彼が行方不明になっても、俺はそのことを秘密にしたままだったのだ。黒子が山にいるのを見たと証言すると、自分が山に行っていることもバレてしまう。自分勝手なことだが、山への立ち入りを禁止されるのではないかと思ってしまって、口にするのを躊躇ってしまったのだ。後から、きちんと言っておくべきだったのでは、と後悔した。しかし、時間が経つにつれて、尚更言い出しづらくなり、今に至るまで誰にも知らせていない。その罪悪感が、今も胸にこびりついている。
黒子が見つかったと言う話は聞いていない。目の前の少年が黒子であるはずはなかった。狭い町だ。起こった出来事はすぐに共有される。
少年は、黒子と同じような水色の髪と白い肌を持っている。その珍しい色彩を、黒子以外で見かけたのは、初めてだった。
少年は、どこに掴まることもなく、ただ静かに、坂の途中に立っている。彼は、山登りには相応しくない白い着物を身に付けているにもかかわらず、息が上がっている様子はない。それどころか、汗一つ掻いていないようだった。
俺は、少年の服装に、何故か、七つ年上の従姉妹が結婚式で着ていた白無垢を思い出していた。彼は、赤の薄羽織を着物の上から纏っている。帯には、赤と金の煌びやかな刺繍が施されていて、目を引く。白い着物という共通点はあるものの、従姉妹の着ていた白無垢とは、似ても似つかなかった。
「……お久しぶりです」
少年はゆっくりと瞬いて、俺の名前を呼ぶ。本当に黒子なのか、と震える声で問いかけると、彼はこくりと頷いた。
「行方不明になったはずじゃなかったのか……?」
黒子は困ったように曖昧に微笑んだ。表情の変化は乏しい。そういえば、そういうやつだったな、と懐かしくなった。
「僕を見かけたことは誰にも言わないでください」
何を言うべきか悩んでいると、黒子は柔らかな声音でそう告げた。耳を打った言葉に、は、と息が漏れる。
「どうしてそんな……!」
俺は思わず声を荒らげた。黒子のご両親が黒子を必死に探していたのを知っている。帰省中に見かけた彼らの横顔は、五年が経った今でも暗く沈んでいた。
「ある人に連れ去られて、一緒に暮らしているんです。僕は彼の花嫁だから」
誘拐。監禁。そんな言葉が頭を過った。それが事実ならば、通報するべきだ。この場に、黒子以外の人影はない。彼を逃すならば、今だった。
「僕はここから出られません。だから、僕が生きていることは知らない方がいい」
こことは一体何処のことなのだろう。周囲に建物は見当たらない。何を指しているのか、分からなかった。
けれど、ただ一つ、確かなことがある。黒子をここから連れ出すべきだということだ。
「馬鹿なことを言うな!」
俺は、声を張り上げた。こんな大声を出したのは、いつぶりだろう。町に戻ろう、と続けようとしたところを、黒子に遮られる。
「それ以上、言わないでください。死にたくはないでしょう?」
服の間に氷を差し込まれたように、背筋に冷たいものが走る。俺と黒子を隔てるように、突風が吹いた。
逃げろ。逃げろ。山が騒めいている。山が警告を発している。黒子に深入りするべきでないと、本能で理解させられる。
幼い頃から、山の意思のようなものを感じることがあった。森の意思と感じ取ったならば、すぐさまそれに従うべきだと経験から知っている。
ここから去るべきだと忠告されているように感じて、山を早々に降った翌日、俺が歩いていたあたりで土砂崩れが起こっていたのだと知ったことがある。足元に気をつけろと注意されているような気がして、地面に視線を落とすと、毒を持った蛇が足の近くを這い進んでいることもあった。
それが本当に山の意思であるはずはない。恐らく、無意識のうちに危険のサインを感じ取って、それを山の意思として認識していたのだろう。
けれど、真実はどうだって構わない。山の意思のおかげで、俺は、頻繁に山に出入りしながらも、一度も大怪我をせずにいられた。今回もこの直感に従うべきなのだろう。
俺は奥歯を強く噛み締めた。目を強く瞑り、大きく息を吐く。その吐息には、落胆が滲んでいた。
「……わかった。お前は、大丈夫なのか」
俺には、いつも勇気が足りない。自己保身ばかりで嫌になる。いつだって、俺は、誰かのヒーローにはなれなかった。
「安心してください。困った人ですけど、彼は僕のこと、大切にしてくれてますから」
黒子は慈しみ深く微笑む。その笑顔が偽りには見えなかった。
本当にこれでいいのだろうか。そう思いながら、踵を返す。逃走を促す山の意思は、木々のさざめきのような声として、頭の中に響くようになっていた。
命拾いしたね。耳元で男の声がした。勢い良く振り返ると、男が、黒子の腰を抱くようにして立っている。
いつの間に現れたのだろう。気配は一切感じ取れなかった。男の髪は血のように赤く、紅と金の瞳は獰猛な野生動物にも似た酷薄さを帯びている。その相貌は不吉なほどに整っていた。彼は黒子と同じように白い着物に身を包み、赤の羽織を肩に掛けている。男が黒子の言うあの人なのだとすぐに分かった。
男と視線が合った。殺される。鋭い視線に、理屈ではなく、そう思った。
俺は考える間もなく、勢い良く駆け出していた。必死に走り、町を目指す。気が付くと、俺は山の麓で寝転がっていた。どうやって山を降りたのかは、よく覚えていない。ただ、息切れが酷かった。
俺は、リュックから水筒を取り出し、スポーツドリンクを飲む。どうにか息を整え、そこで気が付いた。黒子が行方不明になったのは、中学二年生の頃だ。大学一年生にもなれば、そこから身長も伸び、体格も変わる。
けれど、黒子はあの頃のままだった。まるで、時間が止まってしまったかのように、何も変わっていない。
黒子はもう、この世のものでないのだろうか。だから、自分のことは誰にも伝えないで欲しいと言っていたのかもしれない。そんなことを思う。心地良いはずの蝉時雨が、いやにうるさく聞こえていた。
もしかしたら、黒子もあの男も、真夏の見せた蜃気楼だったのかもしれない。そう思ったから、俺はあの出来事を誰にも言わなかった。
けれど、あれは現実だったのではないか、という思いが消えない。それどころか、その疑念は日に日に大きくなっていく。黒子との邂逅を、幻として忘れることはできなかった。
行方不明になったはずの黒子が生きている。そして、あの男と一緒に暮らしている。それは、俺が一人で抱えるには大き過ぎる秘密だ。
だから、俺はこの話をポストに投函することにした。
不思議な話を収集しています。秘密は守ります。俺は、黒子と出会った次の日から、そう記された貼り紙をしてある奇妙なポストを、至るところで見かけるようになった。
初めて目にしたとき、こんなところにポストがあっただろうか、と思った。それは、俺の家から数歩のところに建っていたのだ。そんなところにポストがあれば気付かないはずはないが、見かけた記憶はなかった。
俺は不思議に思ってポストに近付く。しかし、不気味な貼り紙をしてあることを除けば、変哲もない普通のポストだった。
俺が訝しげにポストを観察していると、近所の人に、どうしたの、と声を掛けられた。俺が、ポストが、と口にすると、その人は、え、と不審げに眉を顰める。そんなに変なことを言っただろうか。いや、これ、と指を差そうとすると、ポストは跡形もなく消えていた。
それ以来、そのポストは俺の前に何度も現れた。観察の結果、分かったことだが、そのポストは、俺だけが見ている時にランダムで現れるらしい。場所も時間も問わない。ポストが自分の部屋の中に出現したときは、さすがに驚いた。叫び出さなかったのを褒めて欲しいくらいだ。
俺が東京に戻って来た今でも、それは続いている。恐らく、その切欠は、黒子と会ったことだろう。あのときの話をポストに投函すれば、この奇妙な現象は終わるのではないか、と俺は推測していた。
それに、秘密を一人で抱え込むのも限界だった。あの日の出来事を自分以外の誰かに知っていて欲しいと思う。だから、俺は、このポストを利用させてもらうことにした。
手紙を書いている途中で、思い出したことがある。昔、祖母が教えてくれた話だ。もしかしたら、この出来事に関連しているかもしれない。
かつて、町の人々は、十年に一度、山に生贄を捧げていたのだという。文献も残っていないから、詳しいことは定かではなかった。
祖母の話によれば、どうやら山には、邪神と呼ばれるような神がいたらしい。人々は、その神に滅ぼされないように、定期的に若者を捧げていたのだという。しかも、その風習は、何百年もの間、続いていたらしい。
しかし、あるとき、何人もの陰陽師が町を訪れた。彼らは多くの犠牲を出した末に、神の封印に成功し、それから、生贄の風習はなくなったのだという。人々は次第に、邪神のことは忘れていき、山そのものを神として奉るようになっていったらしい。
その話が真実かは分からない。しかし、山の中には、ひび割れた祠がある。それは事実だ。
俺は、遠目に眺めたことがあるだけで、その祠に近付いたことはない。そこには、黒子がいることが多かったからだ。
もしかしたら、あれが邪神を封じていたのかもしれない。何となく、この予想は間違っていない気がした。ならば、黒子の隣にいた男こそが、そうなのだろう。
もしかしたら、俺を何度も救ってくれていたのは、自分の危機管理能力でなく、山の神だったのかもしれない。ふと、そんなことを思った。俺は、あの男の視線に、抗いようのない死を感じた。それなのに、俺は今、こうして生きている。それは、邪神から山の神が守ってくれたからではないだろうか。
今度、実家に帰省したら、お礼の気持ちを込めて、山の神に何か、御供物を持って行こうかと思う。何度も助けてもらったのに、気付くのが今更になってしまったことが、少し申し訳なかった。
俺は、この手紙がどこに配達されるのかも知らない。でも、これが誰かに届くことを、ただ願っている。
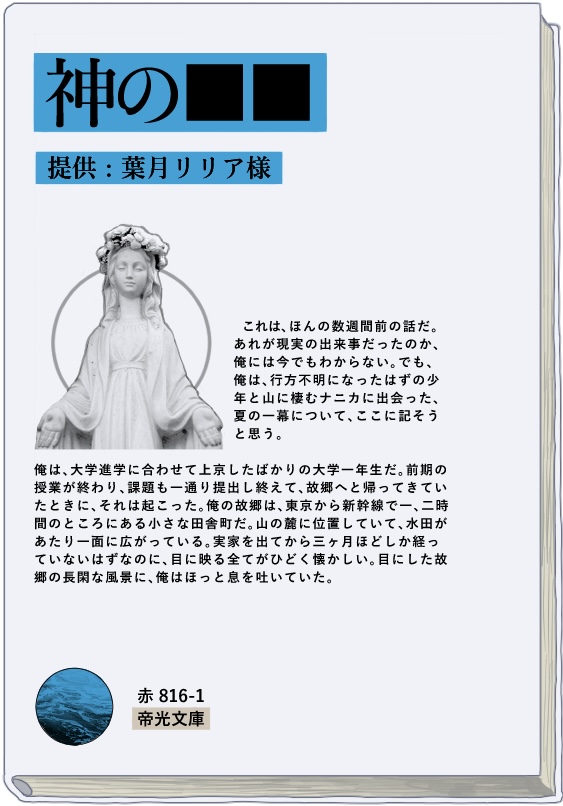
「神の■■」
提供:葉月リリア様
