「バスタブの底に沈む猫」
「社長は、どうしてこの会社を立ち上げようと思ったのですか」
赤司は運ばれてきたコーヒーカップがデスクに置かれたのに気が付き、書類から顔を上げた。
コーヒーを運んできて、そう尋ねたのは秘書の小暮だった。
小暮はキャメルのスーツに身を包み、眼鏡をかけた小暮は頬にほくろがある、どことなく猫に似た雰囲気をまとった、ミステリアスで知的な印象の男である。
一年前に採用したのだが、口が堅く、仕事ぶりも真面目で申し分のない秘書だった。
足を組んだまま、赤司はコーヒーカップを手に取り、ふ、と唇を緩ませ、笑みをこぼした。
「何を聞くかと思えば。ホームページにも沿革は記載しているし、実際、採用時の面接でも触れたのだから、知っているはずだろう?」
「はい。存じ上げております。ですが、もっと詳しく知りたい、と思いまして。確か……社長のご学友が失踪されたのですよね。それで、社長は昨今の情報化社会において、犯罪を未然に防ぎ、セキュリティ関連に力を入れたいと思い、安心安全な社会構築のため、この『OVERKLOOK(オーバークルーク)』を立ち上げたのですよね」
赤司が経営する『OVERKLOOK(オーバークルーク)』は赤司財閥グループの傘下にある、主にGPSなどの通信機器や遠隔技術、防犯関係の機器やシステムを扱う会社である。
紡績から端を発し、発展した赤司財閥のグループでは異色の存在だった。
しかし、新規で立ち上げた事業にもかかわらず、業績はグループの中でも高位にあり、財閥の長である父からも社長としての手腕を認められていた。
赤司はコーヒーを嚥下すると、ソーサーにそれを置いて一呼吸置き、手にしていた書類に再び目を落とした。
「その通りだよ。特に掘り下げるところもないはずだけど、もしかして……密着取材のオファーがあった関係かな」
「はい。社長の生い立ちから会社設立の経緯を私がまとめてテレビ局の担当者に提出しますので。まとめながら疑問に思ったことがあり、お伺いしました」
「……何が知りたいのかな」
赤司は顔を上げると、手にしていた書類をデスクに戻した。小暮はメモを取るために手帳と筆記用具を出した。
「失踪されたご学友はどのような方だったのですか」
赤司はデスクの上に両肘をつけたまま手を組み、その上に顎を乗せた。
「そうだね……オレにとって、親友と呼べる人だったよ。彼とは中学の部活で出会ったんだ」
「確か、社長はキセキの世代……あの、バスケットボール選手として十年に一人の逸材と呼ばれた五人のうちの一人でしたよね」
「なんだか恥ずかしいな。そうだよ。全員同じ中学だった。彼はキセキの世代じゃなかったけれど、幻の六人目と呼ばれていたよ。他の四人のキセキの世代は全力で対戦できる数少ない相手だったから、好敵手という気持ちが強かった。その点、彼は実力に差があったけれど、いつもオレの予想を超えてくる存在だったよ。だから、特別だった。彼には絶対負けたくないと思っていたんだよ」
「社長のとても大切な友人なのですね。……彼はいつ頃失踪したのですか」
「この会社を立ち上げる前だから、そうだな、五年くらい前になるかな」
「どのような経緯でいなくなられたかご存じですか」
「その日は、大学で午前から講義があって、出席したそうだよ。その後、学食で食事をとって、大学の図書室でレポートを書いていたみたいだった。同じサークルの同期が連絡を取ったら、そういう返信が来たそうだからね。夕刻、サークルに顔を出して同期達と会話をした後、アルバイトに向かったと聞いている。サークル仲間もアルバイト先の店長や従業員も別段変わった様子はなかった、と言っていた。アルバイトを終えて帰路に就いたはずだが、その後の足取りがつかめないそうだよ。……携帯も圏外、口座のお金は手つかずのまま、公共交通機関を利用した記録も飲食店や小売店で何かを購入した記録も一切ない」
「……今も見つかっていないのですか」
赤司は眉を潜めて寂し気な表情を浮かべた。
「ああ。残念ながらね。元々存在感が希薄な子だったから、他人の印象に残らず、目撃情報も寄せられなかった。オレ達旧友が何人も血眼になって捜索したけれど、何の痕跡もつかめなかった。警察も防犯カメラを解析して行方を調べたが、ある空白の区間で忽然と姿を消したと聞いている。その間に車はおろか人一人通っていなかったらしくてね。現在に至るまで本人はおろか、所持品一つ見つかっていないんだ。……不思議だろう? ここまでして、手がかりが何も見つかっていないなんて。……こういうのを『神隠し』と呼ぶのだろうね」
赤司の言葉を小暮は静かに聞いた。
……そう。彼は今も見つかっていない。
いなくなった赤司の旧友の名を、小暮は知っていた。
ちゃんと当時の新聞記事を調べたから。
彼の名は黒子テツヤ。捜索願を出され、警察が動いたにも関わらず、五年過ぎた今も行方知れずのままだった。
「社長は……彼がまだ生きている、と思いますか」
小暮の質問に、赤司は眉一つ動かさなかった。
当時の新聞やニュースで赤司はインタビューを受けていた。
強豪校、帝光中学バスケ部の主将をしていた赤司はインタビューを受けても取り乱すことはなかったが、この時ばかりは少し様子が違っていたという。
けれども、五年も過ぎたせいだろうか。今は淡々としていた。
「……そうだね、生きていてほしいとは思うかな。もう一度、会って話をしたいからね。けれど……こんなに時間がたっても何の手がかりもないんだ。難しいかもしれないね」
そう語る赤司はどこか寂し気で、まるで自分に言い聞かせるかのようだった。
おそらく、多くの人の目には、親友をなくしたいたわしい男の姿に映ることだろう。
「……この会社を立ち上げたのは社長の『大切な人が事件や事故に巻き込まれたときの自分と同じ思いをしてほしくない』という願いからでしたね。そのおかげで防犯にも役立っていますし、万が一事件に巻き込まれた場合でも、どんな形であってもユーザーは家族の元に戻れています。……私の父は豪雨による土砂災害に巻き込まれて亡くなっています。懸命の捜索の結果、やっと父の亡骸を見つけたときは悲しかったですが、少し安堵しました。もし、あの時にわが社の技術があれば、もう少し早く父を見つけられていたかもしれない、助かっていたかもしれない、とも思います。……社長もそうでしょう。自分と同じ悲しい思いをする人を減らしたいだけではなく、本当は今も彼を見つけ出したいのですよね。だから、わが社を立ち上げたのではないですか」
そう質問しながら、小暮は赤司がそうは一切思っていないことを見抜いていた。
そんな小暮の思惑を知ってか知らずか、赤司は空気をふ、と揺らすとこう返した。
「そうだね。確かに、そう思って会社を立ち上げたことは間違いないよ。……けれど、オレは今、彼を見つけ出したい、とは思っていないかな」
「……どういうことですか」
小暮の問いかけに赤司は微笑んだ。しかし、その瞳はこちらを見ておらず、遠くを見ているようだった。
「生きていてくれるのならば、もちろん会いたいと思うよ。けれど、記憶を失ったりして、忘れられていたら悲しいだろう。とてもじゃないが受け入れられないよ。それだけじゃない。仮に、今彼が見つかったとして、それが彼の死を決定付けるものなら、オレは見つかってほしくないと思う。明確な死を裏付ける、例えば骸の一部が見つかりでもしたら、彼の死を嫌でも受け入れなくちゃいけないだろう?」
「……社長は彼の死を受け止めるのが怖いのですか」
「そうだね。そうかもしれない。オレは彼の死を受け止めたくないのだろうね」
「でも、それではいつまでたっても一区切りつかないでしょう。たとえ再び生きて会うことがかなわなくとも、せめて連れて帰って弔ってあげたいと思うのが人の情というものではないでしょうか。それが敬い、慈しむということだと思うのですが」
「……オレが彼を見つけ出したくない理由はそれだけじゃないよ。一般的にこういう現象を行方不明とか、失踪とか、神隠しと呼ぶ。中でもオレは『神隠し』という言葉の響きが好きなんだ。『神に隠された』なんて『生きているかもしれないし、死んでいるかもしれない』という神性を帯びた感じがするだろう。だが、一度遺骸が見つかると、どうして失踪したのか、どのように亡くなったのかが分かってしまう。すると、たちまちその神性は失われる。『神隠し』ではなくなり、事件や事故と名の付く陳腐なものになってしまう。……彼は元々神に隠されたような子だったから、そうなってしまうのは非常に残念だよ。死という最悪な結末も否定はできないけれど、遺骸さえ見つからなければ、生きているかもしれないという望みは繋げられる。この『生きているかもしれないし、死んでいるかもしれない』というのが重要なんだ。『シュレディンガーの猫』のようなこの状態がね」
赤司の口ぶりに小暮は確信を持った。
この男は黒子を本気で探そうなどとは思っていない。むしろ、探す気が一切ない。
そればかりか、神に愛されたが故に人目につかぬよう隠された彼という状況に陶酔している。
普通、行方不明になった当事者にただならぬ感情を抱き、あるいは執着しているのなら何が何でも捜索するはずである。
けれど、それをしないからと言って、特別な感情がないとか、執着していないという証にはならない。むしろ逆だと思った。
禍々しいくらいの執着と独占欲の権化。それを傍目からはそう見えぬよう、見せかけているだけ。
「お時間をいただき、ありがとうございます。局には私の方から社長の来歴をまとめて出しておきます」
「ああ、頼んだよ」
「……最後に一つだけよろしいでしょうか」
「なにかな」
赤司は小暮の問いかけを何気なく聞きながら手を伸ばし、机上の書類を手にした。
「社長は猫を飼っていらっしゃいませんか」
「いや。昔、飼っていたことがあるけれど、今はいないよ」
小暮の問いかけに赤司は動きを止めることもなく、自然に書類に目を落としながらそう答えた。
……赤司征十郎は黒子テツヤの行方を知っている。
先刻語った会社設立の経緯は建前でしかない。真の目的は――。
「……ただの猫ではありません。『シュレディンガーの猫』ですよ」
確信を突く小暮の言葉に、赤司は書類から顔を上げた。
赤司は目を見開くことも、視線を泳がせるようなこともなかった。
ただ、恐ろしいくらいの微笑を湛えただけだった。
しかし、小暮は無数の鋭い切っ先がこちらに向けられているかのような殺気に充てられ、背筋を凍らせた。
……それは、確実に赤司征十郎の忌諱であった。
「飼っていないよ」
************************
自らが建てた高層マンションの最上階に赤司は一人で住んでいる。
当然、セキュリティシステムはすべて『OVERKLOOK』のものを採用しており、虫けら一匹通さない。
マンションのエントランスは顔や指紋などの生体認証が必須だし、部外者の入退室には専用のリストバンドの着用が義務づけられているほどだった。
カードキーを切ってエレベーターに乗り、最上階で降りた。
最上階はワンフロアになっているので、赤司はカードキーを切って入室し、帰宅した。
通路を抜けると、観葉植物が置かれていて、市街が見渡せる眺めの良いテラス付きの広いリビングにたどり着く。
夜景が美しく、シンと静まり返った伽藍洞に足を踏み入れると、赤司はカバンをソファの上に置いた。
そして、そのままバスルームへと向かうのが日課だった。
しかし、赤司はリビングの奥、すぐ横の区画に設けられているバスルームには向かわず、リビングを抜けて元来た道を戻った。
寝室もトイレも素通りし、通路を抜け、赤司は玄関近くの防火扉の前に立った。
すぐ隣にある配電盤と思しきボックスを開けると、銀色のテンキーが並んでいる。
赤司はそこに慣れた手つきでパスワードを入力した。
すぐさま、ピピー、という解錠の電子音が鳴り響き、赤司は防火扉のケースハンドル錠をひねって扉を開けた。
扉の向こうにはエレベーターくらいの大きさの部屋があり、さらにレバーハンドルの扉が現れる。二重扉になっているのだ。
赤司は首にかけた鍵を衣服の中から取り出して、そこの鍵穴に差し込み、錠を開けた。
カチャ、という音と共に解錠すると、レバーハンドルを捻って扉を開ける。
扉を開けた先にはもう一つリビングがあった。
しかし、その様相は先刻のリビングとは異なっていた。
まず一つ目に、市街が見渡せるガラス張りの窓のすぐ横にシャワー付きのジャグジーが置かれている。
これがあるためか、フローリングの床は部屋の中ほどで途切れており、わずかな段差の下がタイル調の耐水性の床になっていた。
観葉植物が置かれたフローリング部には壁に埋め込み式の液晶テレビがあり、ソファとテーブル、そしてキングサイズのベッドが置かれている。
薄暗いその空間で、ジャグジーの中に居る人影がこちらを振り返った。
向けられた視線はいとも簡単に胸をかき乱すほどの妖しい色香を孕んでいるのに、窓ガラスに映るどんな街の明かりよりもあたたかくて明瞭な光を帯びている。
濡れた髪からしたたる雫が弾け、夜景に映えたその姿はまばゆく、人魚と見まがうほどの美しさで赤司を魅了した。
「おかえりなさい、赤司君」
その微笑一つで、一日の疲れが一気に吹き飛び、魂が洗われたような気がするのは、神に愛された彼がまた一歩、神に近づいた証拠かもしれない、と赤司は思った。
「ただいま、黒子」
赤司はそういうと、歩を進めながら、ネクタイを緩めて首元から引き抜き、床に落とした。
「待ちくたびれただろう。お前はここから出られないのに寂しい思いをさせてしまったね。少々処理に手間取ってしまってね。遅くなってしまった、すまない」
黒子はバスタブの中でくるりとこちらを向くと、縁に両腕を置いて寄り掛かり、小首をかしげて微笑んでみせた。
「気にしていませんよ。お仕事、毎日お疲れ様です。今日も一緒に入りますか?」
ジャケットを脱ぎ捨て、シャツのボタンをはずしながら、赤司は頷いた。
「ああ。そうさせてもらうよ」
黒子がバスタブの中から両腕を開いて赤司をいざなう。
……リビングの向こう、フローリングの床側の壁に埋め込まれた液晶テレビに映りこんだ女性キャスターの声が聞こえてきた。
「先ほど入ってきたニュースです。〇×市の林道で男性の遺体が発見されました。男性は二十代とみられ、キャメルのスーツ姿で左頬にほくろがあり、眼鏡をかけているということです……」
バスタブの中に赤司が入ると水位が上がる。必然的に黒子はよりいっそう深く身を沈めることになった。
湯を介して意識も体も延長して、ひとつながりになっていく。
細胞の隙間を満たした湯に身も心も染まって毒されていく様な気がした。
……いや。この一風変わったバスルームに閉じ込められたまま、逃げようなどとは微塵も思わない時点でもうすっかり毒されているのだろう。
そもそも、内から解錠できない仕組みの部屋である上に、全裸では逃げられるはずもないのだけれど。
湯船に身を沈めた赤司は液晶テレビでニュースキャスターが語っている内容に意識を向けた。
「見つかるのが早かったね。まあ、防犯カメラやシステムのデーター改ざんは完璧だから、足が付くことはないだろうけど」
「仕事で遅くなったのだと思ったら……また、ですか。ダメですよ、もう」
「仕方ないだろう。オレから黒子を奪おうとしたんだから、当然の報いだよ」
「赤司君が捕まったら、ボクが困ります。……もう、こんなことやめましょう? 罪を重ねる必要ないんです。ボクはキミの傍から離れませんから。ん……」
ちゃぷ、と水面が揺れ、跳ね上がった。
赤司が黒子の唇を自身のもので塞いだからだ。
……よほど耳に痛かったのだろう。
「万が一にもそんなことはありえないよ。黒子は何も心配しなくていい」
「……」
それ以上、何も言わなかった黒子に赤司は満足げに微笑して頷いて見せた。
何を言っても無駄なことを五年かけて教え、骨身に沁み込ませている。
……そう。それでいい。
オレだけが黒子を知覚できればいい。その胸をオレ以外の者や物事で煩わせ、そのまっすぐでいじらしい瞳を涙で濡らす必要はない。
オレの、オレだけのシュレディンガーの猫でいてくれさえすれば。
赤司は猫を愛でるかのように黒子の顎から喉にかけて手を伸ばすと、そっと指で撫でた。
……歪んだ愛という名前の醜いエゴ。
湯船に大波ができて体がたゆたうと同時に、赤司に唇も視界も覆われて、黒子はバスタブに沈められた。
子猫のようにすり寄ってくる赤司に異常性や危うさの片鱗は見られない。
むしろ、「ボクが傍にいてあげなくちゃ、この人はダメなのだ」と思わせられ、庇護欲をそそられてしまう。
憐れだが、どうしても憎めないこの男を、黒子はこの上なく愛おしく思った。
歪んだ愛も、醜いエゴも、秘密も、狂気も、罪も、なにもかも。
ステップを踏んで意気揚々とバスタブを飛び出しては、弾けて香りを振りまくシャボンの泡で、すべてを覆い隠して。
ゆっくりと底に沈んでいく重い愛にすっかり飼いならされた猫は、今日も今日とて魚のようにバスタブの水槽を自由に泳ぎ回るのだった。
終
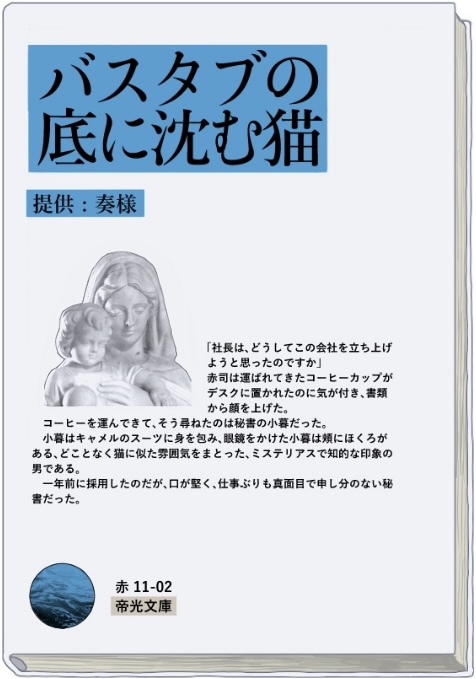
「バスタブの底に沈む猫」
提供 : 奏様
