「二人で楽しもうじゃないか」
赤司くんと喧嘩をした。
言ってはならない言葉を口にしてしまった。
それに気づいたのは彼が傷ついた顔をしたから。
僕は息を飲み、なんてことをしてしまったんだと思った。
でも、口から出てしまったものを取り戻すことはできない。
無かったことにすることも。
咄嗟に出てきてしまったその言葉はきっと僕の本音だったに違いない。
「……っ、さよなら赤司くん」
僕はぎゅっと目を瞑り、目の前の彼から目を反らした。
現実を、目の前の光景を、受け入れることが僕にはもうできなかった。
そのまま体の向きを変え、赤司くんに背を向けて歩き出した。
ハッ、ハッ
息が上がる。
――息苦しい。
乱れる呼吸に僕はいつのまにか走り出していることに気が付いた。
――こんな、こんなつもりじゃなかった。
でも、きっと遅かれ早かれこうなる未来だった。
それが早まってしまっただけ。
それだけの話だ。
グズッと鼻をすする。
ぼやけた視界を手の甲で乱暴に拭った。
赤司くんと恋人の関係になって五年目。
同棲がしたいという赤司くんの何度目かのお願いを断った日だった。
僕たちは、学生の頃の拙い恋愛から大人の恋愛へと変わっていった。
ずっと穏やかな恋人同士だったと思う。
でも、互いに社会人になり、変わりたくないと思っていても周りの環境がそれを許してはくれなかった。
狭い視界が広がっていき、僕たちの関係が世間一般的ではどういう存在なのかも知ることとなった。
知りたくなかった。でも、知らなければならなかった。
彼の家柄だって知っていたはずなのに知らない振りをしていた。
知らない振りができなくなっただけなのに。
年を重ねると人との関係性は広く浅いものとなっていく。
そんな中、赤司くんは学生の頃から変わらずに僕を見続けてくれる。
何事も僕を優先してくれるのだ。
それが嬉しくて、時に怖くて、幸せで、息苦しかった。
些細な衝突が積もりに積もっていた不安を崩してしまった。
それが言葉となり彼を傷つけてしまった。
きっとこのまま彼のそばに居たら僕はまた彼を傷つけてしまうかもしれない。
それが怖くて、恐ろしくて、僕は彼と別れることを決意した。
それが数十分前の出来事だった。
涙で滲んだ視界の中、スマホの画面で飛行機の日程を見つめる。
「……失恋をしたら旅行と相場は決まっていますよね」
今度の連休に赤司くんと泊りに行く予定だった。
それを一人で行くだけ。それ、だけ。
決済ボタンをタップしてから、画面を暗くする。
そこに映った自分の表情は見ていられないほど酷いものだった。
搭乗口から飛行機に乗り込む。
チケットと席の番号を見返しながら畿内を歩いた。
「あっ」
目的の場所に辿り着くと、隣席にあたる窓際に座っている人がいた。
帽子を目深に被っていて肘をついて俯いていたが、顔は見えないのに様になる人だった。
僕はその人の隣の通路側だ。
「お隣失礼します」
一言断ってから素なりに座ると、僕の声に反応をした隣の席人が顔を上げた。
「……えっ!?」
赤司くん!?
「いだっ!」
ガタッと飛び上がるように立ちあがったことで荷物棚に頭を思いっきりぶつけてしまった。
「お客様!?」
「ああ、すみません。恋人が窓際に座りたいと駄々を捏ねたので譲ってあげると言ったのがそうとう嬉しくて飛び上がってしまっただけです」
ぶつけた頭を撫でられながら窓際に押し込められる。
「あのっ、僕やっぱり降りま、もごっ」
「お騒がせしてすみません」
「そう、ですか。すぐに離陸しますのでお席に座ってお待ちください」
「はい」
CAが居なくなると口を塞がれていた手が離れる。
急いで立ち上がろうとするが、ポンと音が鳴り離陸の合図が入ってしまった。
シートベルトを赤司くんによって閉められ、ここが飛行機の中であり、窓際に押し込められたことでこの席から逃げ出すこともできないと今更気づいてしまった。
ギロリと赤司くんを睨みつける。
「何でキミがここにいるんですか」
「何故? もともと旅行に行く約束をしていただろう?」
「目的地は決めていませんでしたよね? それなのに何故」
「ああ、相談をされなかったから悲しかったよ。そうそう黒子が選んだホテルは少々不便な場所だったから違うところに変えておいたよ」
「は、い?」
僕はそもそも一人部屋を予約したんですが。
「楽しみだね、黒子」
手を握られ、微笑まれる。
――ああ、この人はずっと僕を手放さない気なんだ。
だから、僕が怒っていた理由もあの日別れたことも気にしていないんだ。
別れるという選択肢が彼にないから。
窓の外に視線を向けると飛行機が飛び立つところだった。
パチパチと機内で小さな拍手が聞こえた。
「二人で楽しもうじゃないか」
笑みを向けられ、ぞわりと産毛が逆立った。
視界が広がったと思っていた。
認識も恋愛も、価値観も変わったと思っていたんだ。
赤司くんはずっと、あの時から変わっていない。
ずっと、僕だけを見つめている。
僕はとんでもない人と付き合っていたのかもしれないと今更思い知った。
彼に見つかったあの時から、逃げることなど今更無理だったのだ。
END?
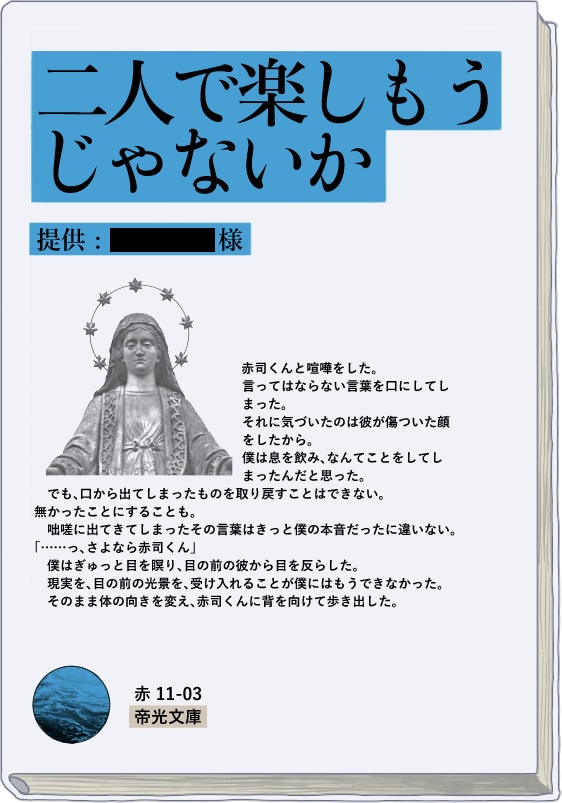
「二人で楽しもうじゃないか」
匿名の提供
