「愛の普遍性について」
「もし俺が死んだら、俺の死体は黒子にあげる」
唐突に赤司がそんなことを言った。
少し長い信号を待っているときだった。片手には最近ハマったプレミアムアイスの入った袋。左手は、自然と黒子の右手を握っている。その温度はいつもと変わらないはずなのに、言葉の内容のせいで妙に冷たく感じた。
黒子は反射的に握られた手を引っこめ、心底嫌そうに顔を歪める。
「え、いらないです。普通に」
即答する黒子に、赤司はきょとんと首を傾げた。キョトンとした顔が妙に可愛くてイラッとする。赤司は平然とした顔で続けた。
「……最近の臓器は高いらしいよ?」
「何の話をしてるんですか。ここは平和な日本ですよ? 倫理観どうなってるんですか」
「ドナー制度とそう変わらないだろう。むしろ黒子ならきちんと扱ってくれそうだし」
「変わりますよ! ほら、青信号です。パッパと歩いてください」
黒子は逃げるように足を踏み出す。しかし赤司は当然のように隣に並び、歩幅を合わせてきた。コンビニの袋がカシャカシャと音を立てる。
「黒子は真面目すぎるところがあるよね」
「キミも真面目なはずなのに考え方が突拍子もなくておかしいんですよ」
「……褒めてる?」
「今の言葉のどこに褒め要素が?」
黒子は辛辣に言い放ち、再び手を繋ごうとした赤司の手をぱしっとはらう。それでも赤司は笑っていた。むしろ楽しげですらある。
黒子はため息をついた。こんなことなら、コンビニにアイスを買いに行こうなんて言わなければよかった。赤司のヘンテコ発言はこれに限ったことじゃないけれど、今日のは話の方向性がかなりギリギリなラインで、受け答えにどうにも悩まされる。
「ボクが死んだ時、死体の所有権はキミには渡しませんからね」
「誰に渡すんだ?」
「普通にすぐ燃やしてもらいます。死体の所有権の主張なんてする意味ありませんし」
「……燃やしちゃうんだ。勿体ない。その僅かな時間でもいいから、俺に預けてくれたらいいのに」
黒子はそんな赤司の言葉に喜ぶ訳もなく、立ち止まり、肩をすくめた。心底呆れつつも、ふと赤司の横顔を見る。赤司は相変わらず意味のわからないことを言っている——けれど、その横顔はどこか少しだけ優しい顔をしていた。
夜の住宅街は静かだ。アパートまではあと五分くらいだろうか。近所迷惑にならないように声を潜めて会話をする。
「どうして急にそんな話をしたんです?」
「別に。変な話でもないだろう。人間、いつ死ぬかなんて誰にも分からない。死後の自分を誰に委ねたいかくらい、考えて当然のことじゃないかな」
赤司の主張は分かるようで分からない。死後の自分を適当に扱われたらたしかに悲しいけれど、たとえ身寄りがないとしても今の日本でそんなことが行われる可能性は無いに等しいだろう。
何より、まだ社会人にもなっていない年齢で死後の自分のことを考える人間はそう居ないだろう。
言い方は軽いのに、声の奥にはほの暗い静けさがある。普段絶対に出さない種類の赤司の“本音の匂い”が一瞬だけ覗いた気がして、胸がざわついた。
「でも……キミがボクにそんなこと言うのは意外です。赤司くん、自分の方が長生きするに決まってると思ってそうなのに」
一瞬だけ視線が交わる。赤司は少し驚いたような顔をしたあと、何か言いかけて、それを飲み込み、穏やかに微笑んだ。
酷く、美しい笑みだった。
「……まあ、周囲と比べても、わりと丈夫な自信はあるよ。でもね——」
そこで赤司はふと立ち止まり、黒子の前髪にそっと手を触れた。さっきまで繋いでいた右手は暖かい。さらりとおでこを撫でる指は細くて、指の隙間から見える赤司の顔はなんだか泣きそうな顔をしていた。
「人は、本当に唐突に死ぬ。俺も、お前も」
否、泣いていたのかもしれない。黒子の視界は今赤司の右手によって、ほとんど奪われているから分からないけれど。
撫でられた髪がくすぐったくて、黒子は小さく肩を揺らす。赤司は撫でる手を止めない。黒子も黒子で、その手を止めようとは思えなかった。
「だから、死んで“生き物”じゃなくなった自分くらい……大切な人に触れていてほしくて……」
変かな、と赤司は小さく漏らす。黒子はそれに左右に首を振ることで応えた。赤司の嬉しそうに小さく笑う。
指の隙間から赤司の顔を見た。どこか寂しげで、そして確かに愛に満ちていた。黒子の胸がきゅっと痛む。
そんな願い方をされるのは、正直ずるい。黒子は頭を撫で続ける赤司の手を掴んで引き寄せた。油断していた彼は簡単に黒子の目の前へと引っ張り出される。
目線が交わる。黒子は笑った。
「……でも、ボクはキミに死体の所有権を譲りたいとは思いません」
「どうして?」
黒子は更にもう一歩近づき、赤司の胸ぐらに軽く手をかけて顔を上げる。
もうそこにはなんの距離もなかった。
赤司の呼吸が止まる。 少ししめった唇を開いて、黒子は言う。
「キミを置いていく未来なんて、最初からボクの選択肢にないんです」
死体の所有権なんて、くれてやるつもりなんてなかった。人はいずれ死ぬ。どこかのタイミングで、何かをきっかけにして最期には死ぬ。そのタイミングはいつかなんて分からないし、どうしてなのかもその時にならないと分からない。
だからこそ、先に死んでやる気なんて少しもなかった。特にこんな、死後すら寂しさを感じてしまう寂しがり屋な恋人を置いて死ねるほど、黒子は愛に鈍感ではない。
黒子の言葉に赤司は驚いたように瞬きをしたが、すぐにゆるく微笑み、黒子を抱きしめた。
その顔は慈愛に満ちている。
「……それは、黒子らしいな。ずいぶん傲慢で、嬉しい答えだ」
黒子も赤司の背に手を回し、小さく息を落とした。死んでもなお、愛する人の近くにいたい。
けれど、それよりもずっと前に死ぬまでおまえの隣にたつ。多分これ以上の言葉なんてこの世には存在しないだろう。
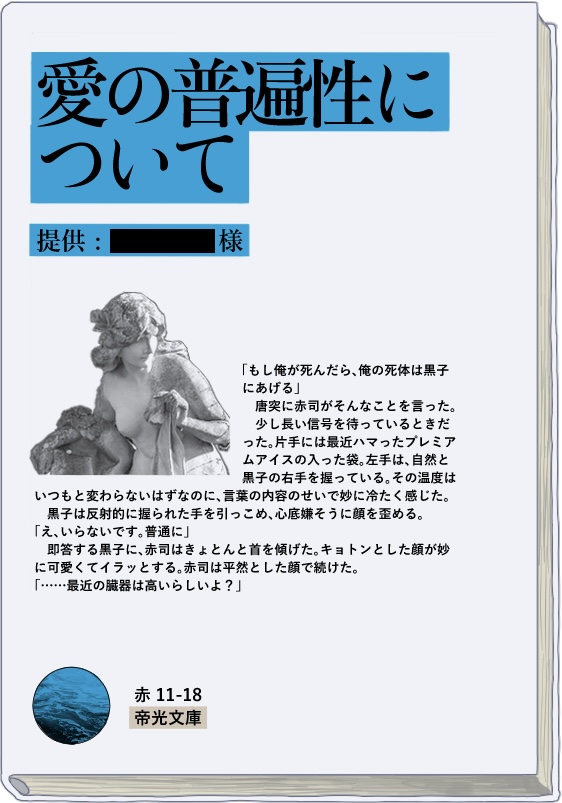
「愛の普遍性について」
匿名の提供
