「予定調和の絡め手」
顔も名前も知らない相手から探されるなんて、初めての経験だった。
お前のことを聞いて回ってたヤツがいたぞ、と同じゼミの友人に言われたのは数日前のことだ。事実として、その時に初めて苗字を聞いた。向こうはアカシ、と名乗ったらしい。どういう字で書くのかは当然分からず、下の名前も不明。困惑が表に出てしまったのか、知らないヤツだったなら聞かなかったことにして、と逆に気を遣われた。
「ちなみに男だったよ。赤い髪で、びっくりするくらい顔がキレーな。年は俺らと同じくらいに見えたけど、もしかしたらちょっと年上かもなあ。めちゃくちゃ高そうなスーツを着てた」
やっぱり誰も思い当たらない。だが、わざわざ知らせてくれた友人を、こちらの事情で足止めするのはさすがに気が引ける。小さいころに会った親戚がそんな名前だったような、と無難な嘘をついて話を終わらせようとした。
「……ならいいんだけどさ。連絡先を教えてくれってのも言われて、そっちは断っといたぞ。だからあいつ、しばらくはこの辺をうろついてるかもしれねーから、気を付けてな」
誤魔化したのがバレた気がしなくもないけれど、あいにく藪をつつく趣味は無い。そのままお礼を言い、友人とは別れた。素知らぬ顔をするのはわりと得意なほうだ。さっきうっかり顔に出してしまったのは、予期せぬ状況だったからということにする。それはさておき。
アカシという名前に覚えがないか、もう一度頭の中を探した。男で、赤い髪で、友人曰くとても顔が良い。年齢は、ぱっと見で自分たちとあまり変わらなかったようだ。ただ、服装からすると同じ大学生ではなく、社会人の可能性も十分にある。
特徴としてはかなり分かりやすい。思い出せる範囲で交友関係を辿ってみたが、やはり該当する人物はいない気がした。
「ちょっと怖いな……」
誰に言うともなく呟いた一言は、周囲のざわめきにかき消される。敷地は広いが生徒数も多いこの大学の構内なら、無関係な人間が多少混ざっていたとしてもほとんど気付かれない。つまり、本当に知り合いかなんて本人以外は分からない、ということだ。何の用事かは見当もつかないが、気の良い友人から言われたとおり、当分は赤い髪の男に注意しておこうと心に決めた。
――――心に決めたことではあったのだが。
「知っているかもしれないが、ずっと君を探していたんだ」
赤い髪、驚くほど美しいつくりの顔、高そうなスーツに、同年代くらいの見た目。友人から聞いたままの容姿を持った、実に目立つ男が間近にいる。背後から肩を軽く叩かれて、振り向いた先にいたのが彼だった。しかも吊り上がった切れ長の双眸は、よく見ると赤と金のオッドアイだ。現実味がないほどの秀麗な顔立ちに、ついまじまじと見つめてしまったのは仕方ない反応だと思う。
現に視界の端の何人かも、びっくりした表情で彼を二度見していた。身長は平均程度の自分より少し高いくらいだが、モデルだと言われても全く違和感がない。普通に生活していれば、滅多にお目にかかれないレベルの美形だった。
「ああ、失礼。名乗りもせずに不躾だったな。僕はアカシという者だ。君から話を聞きたくてね」
どちら様でしょうか、と尋ねるよりも先に相手が名乗った。ごく自然な動作で名刺を差し出されて、少し逡巡した後に受け取る。何の変哲もない白い長方形の紙には、素っ気なく男の名前や勤務先、役職、連絡先などが印字されていた。
赤司征十郎。それが彼の名前らしい。なんというか、これ以上ないほどぴったりな響きだと思う。名刺の下部に記載された会社名がかなり有名な大企業で、大学生にも見える外見の割に、ずいぶん責任の重い地位に就いていることも分かった。だからといって、初対面の相手に対する警戒が解けることはないけれど。
カバンから取り出した財布に名刺を片付けてから――まだ大学生活を謳歌しているので、名刺入れなんてものは持ち歩いていない――改めて赤司さんの方へ向き直った。
「……ええと、聞きたいことって」
「単刀直入に言おう。黒子テツヤ、という人物に君は心当たりがあるはずだ」
瞬間、思わず息を呑む。身体が硬直してしまうほど驚いた。
どうしてその名前を、という返事が喉までせり上がる。でも結局声にはならず、無意識に浅くなった呼吸が言葉をかき消した。何で今更。辛うじてそれだけは言えたつもりだけど、本当に伝わったかは分からない。
――――だって黒子くんは。真新しい高校の図書室で、いつも物静かに本を読んでいた友人は。幻みたいにいなくなって、そのあと。
「もう誰も『覚えていない』のに、何で」
そこから先はつっかえたように出てこなかった。何を言うべきかも思いつかない。
「さて、何故だと思う? 答えが知りたいのなら教えるのも吝かではないが、さっき言ったとおり君には聞きたいことがあってね。ここは交換条件といこうじゃないか」
優雅に口を開く目の前の男は、完璧なアルカイックスマイルを浮かべている。こちらの様子がおかしいのは承知した上で、何事もないように掛けられた声は、王者然とした威圧感が漂っていた。短い時間で、ごく自然に会話の主導権を握られたと感じ取る。
「君は僕に黒子テツヤのことを話す。その代わりに僕は君の疑問を解消する。もちろん、お互い嘘は無しだ」
悪い内容ではないだろう、と。どこまでも余裕を崩さないまま、赤司さんは返事を待っている。まるで最初から、こちらが受け入れると知っているかのように。実際、選択肢に否の答えは用意されていない気がした。きっと考えすぎではないだろう。言葉にするのが難しいけれど、何となく彼は人を従わせることに長けていそうな雰囲気があった。
「でも、初対面の人をいきなり信用するのは……」
「……へえ、中々に慎重な返事だ。賢い相手と話すのは嫌いじゃないよ」
整った目元がなだらかな弧を描く。同時に、左右で異なる色合いの瞳が愉快そうな感情を滲ませた。顔のつくりも相まって、どことなく獲物を前にした猫を思わせる。ただし、猫は猫でも可愛らしいタイプではなく、もっと獰猛で力強いネコ科の獣の方だが。
「それくらい君にとっては大事な『秘密』というわけか」
血のように真っ赤な右目と、不純物の無い黄金色の左目。そのふたつがほんの一瞬、不穏な光を帯びて輝く。こわい。本能的な直感が心臓の鼓動を速めた。思わず後ずさろうとして、足をぎりぎりで踏み留める。普段はいるんだかいないんだか分からない、プライドとか意地という類の感情が珍しく自己主張をしていた。
「おや。ずいぶん怯えた目をしているね。どうしたんだい」
「――――誰のせいだと」
多分、この男のような態度こそ白々しいと言い表すに違いない。文句のひとつでも言ってやりたいが――この際自分の方が年下だということはどうでもいい――今しがた直面したこわさは紛れもなく本物だった。いっそ、彼との『取引』に応じてさっさとお帰り頂いたほうがいいかもしれない。今更……本当に今更、黒子テツヤの何を聞きたいのかは知らないけれど。
「生憎と僕には覚えがないな。まあいい、どうやら少し考えが変わったみたいだからね」
場所を移そうか。心を読んだとしか思えないタイミングで、赤司さんは話の続きを口にした。君の希望に合わせるよ、とも。予め決まっていたかのように、何もかもが淀みない。悔しいが、この男を会話で言い負かせる結末は想定できなかった。
仕方ない。こちらを遠巻きに見ている何人かには知らないふりをしつつ、大学の正門の方へ歩き始める。せめてもの意趣返しとして、赤司さんには何も告げなかった。我ながら子供っぽい自覚はあったし、効果もおそらくゼロに等しいだろうけれど。何せ背後の足音は、戸惑う気配も迷う素振りも感じさせなかった。
憂鬱だ。
この後話さなければならないはずの内容も、その相手も。自然と重い溜め息が零れる。最近ようやく、当時を――――黒子くんのことを覚えているのが自分だけかもしれない、という現状を受け入れられるようになってきたばかりだった。それなのに、彼は『過去』にすることを許してくれないらしい。
「何から話せばいいんですか」
大学からほど近いマジバは、いつも適度に混雑している。お世辞にも静かとは言えない店内の、やや奥まった席で対面になるよう腰を下ろした。しんとした空間より、常に誰かの話し声や物音がする場所の方が、案外人に聞かれたくない話をするのに向いている……らしい。誰の意見かは言うまでもない。
半ば予想どおり、ファストフードのチェーン店と、向かいに座る赤い髪の男は驚くほど相性が悪かった。素人が切り貼りしたみたいに周囲から浮いている。なのに、不思議と彼に注目する利用客はいなかった。さっきまでとは大違いだ。出入りが多く活発な分、わざわざ他人に関心を向けることもあまりないのかもしれない。
「自分から切り出すとはいい心がけだ。では、黒子テツヤが消息を絶った日のことを聞こうか」
ここまで来て先延ばしにはしません、という返事を飲み込む。別にどう思われようと――赤司さんが言うところの――『取引』が終われば、今後関わるつもりはない相手だ。
「……あの日は黒子くんと待ち合わせをしていました」
鍵の掛かった箱を開けるように、ところどころ霞み始めた記憶を呼び起こす。当時、課題で使う古い書籍を探していた際、偶然それが彼の私物にあると知った。確か、約束を取りつけた前日のことだ。提出期限が迫っていた個人的な事情もあり、なるべく早く貸してほしいと多少無理を言った覚えがある。
「午後の授業が終わった後なら、ということだったので、大学の図書館で合流することにしたんです」
予め時間割を確認していたため、自分が先に図書館へ着いたことは覚えている。
「だが、黒子テツヤは現れなかった」
そのとおりだった。赤司さんの言葉に頷く。日が暮れても待ち人は現れず、結局閉館時間が迫って大学を後にした。急用でも出来ていたのだろうかとスマホを確認したけれど、新しい連絡はなかった。夜に届いた了承の返事が最新のまま、現在も更新されていない。
「意味も無く約束をすっぽかすような人間じゃないことは知ってました。だから翌日、共通の友人に黒子くんを見ていないか尋ねに行ったんですが……」
結果が芳しくないだけであれば良かった。待ち合わせを反故にされた憤りは湧いたかもしれないが、あくまで一次的な感情だ。それに、自分だって過去に――彼相手ではないが――うっかり何時間も人を待たせた経験がある。だから大して重くは考えていなかった。いっそこっちからメッセージを入れてみようか、とも思っていたくらいだ。
「そんな奴いたっけ、と開口一番に言われました。それから全然記憶にない、とも」
「……僕ならまず性質の悪い冗談を疑うが」
「もちろんそう考えましたよ。でも、つまらない嘘を話している様子じゃなかった」
他人の機微には比較的聡いほうだと思う。正直、目の前の人物に関してはほとんど真意を読めないけれど、ある程度付き合いのある相手なら、本気か嘘かくらいは見ていれば分かる。だから、友人の戸惑いや怪訝な表情が、咄嗟に作られたものではないと確信できた。
「本気で、黒子くんが誰か分からないようでした。彼はその場でスマホの確認もしてくれたんですが、そこに黒子くんの名前は無かった」
「そう。僕自身がその場にいたわけでもないし、君の『見たもの』を信じるとしよう。他も似たような状況だったのか?」
今も消し切れない虚しさが、じわりと込み上げてくる。
「少なくとも聞いて回った限り、みんな黒子テツヤを知らないと答えました。データ上にも残っていませんでしたね」
昨日までそこにいたはずの彼は、たった一晩で忽然と『消えた』。姿を見せなくなっただけではなく、大勢の人間の記憶そのものからも文字どおりいなくなってしまった。どうして自分だけは覚えているのか、黒子くんがいなくなった理由はなんなのか。言葉で説明できない現象は多く、今もほとんど分からないままだ。
「なるほど。……君は冷静だな。もう少し感情的になるかと思っていたよ」
「黒子くんがいなくなって二年近く経っていますから。当時よりはいくらか気持ちの整理がついてきただけです」
時間が癒してくれる――――というと陳腐な言い回しだが、淡々と過ぎていく日々に和らげられた悲しみがあるのは事実だった。しかしそんなことよりも、さっきからずっと頭の中で膨れ上がる疑問があった。
「ひとつ聞いていいですか」
「何かな」
「……どうして疑わないんですか? 自分で言うのもなんですけど、今かなり荒唐無稽な話をしていますよね」
他人の記憶からも消えた状態で人がいなくなるなんて、どう考えても現実で起きるはずがない。ふざけているのかと腹を立てられても文句は言えないだろう。実際、もし自分が聞く側の、それこそ赤司さんの立場だったらまず信じられる気がしなかった。もちろん、話した内容に嘘はひとつも混ざっていないけれど。
いくつかの相槌と先を促す言葉。向かい合わせの美しい男は、それだけしか口にしていない。わずかな疑問も零していないのだ。少し会話をしただけで、彼が理知的で聡明だということは――垣間見えるこわさは一旦置いておくとして――分かる。だからこそ、この状況が余計に不自然に感じられた。
「あなたが本当に知りたいことは、別にあるんじゃないですか」
真意の読めない仮面みたいな微笑が、不意に楽しげな表情へと変わる。
「君の話を聞いた後は、僕が君の疑問に答える。そういう『取引』だったね」
「話を逸らさないでください」
「逸らす? そんなことをする理由は無いよ。元より僕の目的はこれから適うのだから」
どういう意味ですか、と全容の分からない答えに苛立ちつつ問い返そうとした時だ。周囲の違和感にようやく気が付いた。さっきまでと変わらず他の客の姿はいくつも見えるのに、彼らのざわめきや物音が一切聞こえてこない。まるで隔離された個室みたいに、お互いが口を閉じればしんと静まる。
どうして今まで違和感を覚えなかったのか、自分を問い質したいくらいだった。
「あなたは……何者なんです?」
「はは! ようやくそれを確かめる気になったのか」
心底愉快だと言わんばかりに、赤司さんは声をあげて笑った。異なるふたつの色を宿した瞳は、どちらも酷薄な輝きを宿している。もしかしたら、実験中のマウスはこういう目で見られているのかもしれない。
「僕は赤司征十郎に決まっているだろう。君にもそう名乗ったはずだが?」
「ふざけないでください! 聞きたいのはそういうことじゃなくて――――」
「心外だな。僕は質問に正しく答えているよ」
聞き分けの無い子供を前にした時のような表情が、彼の綺麗な顔に浮かんだ。
「むしろ君に問いたい。君の『友人』である黒子テツヤは本当に存在しているのか、とね」
「なっ……! 彼に関して尋ねてきたのはあなたの方でしょう!?」
訳が分からなかった。にわかに考えるべきことが増えすぎて、頭がパンクしそうだ。そのせいか、聞き取れるはずの言葉が全て知らない単語に思えてくる。
「何か勘違いをしているようだな。僕は今、君の『友人』の、と言ったはずだ」
「どう違うって言うんですか? ボクは言葉遊びをしたいわけじゃない!」
論点をのらりくらりとずらされて、カッと頭に血が上った。感情を窺わせない赤と金の双眸はどこまでも冷徹だ。こちらの反応を試すような視線に少しだけ落ち着きを取り戻し、テーブルへ拳を叩きつけることで込み上げた衝動を我慢する。瞬間、かなり大きな音が響いたが、やはり誰一人としてこちらを見ようとしない。
「……本当に……何なんです、一体……」
どっと疲れが押し寄せた。無意識にくたびれた声と溜め息が零れ落ちる。この異様としか言いようのない状況だけでも手に余るのに、赤司さんの捉えどころのない言動が更に思考を鈍くさせた。いっそ頭を抱えて蹲ってしまいたい。
「仕方ない、少し言い方を変えようか。僕が探している黒子テツヤは確かに存在する。だが、君が『友人』だと認識する黒子テツヤは、どこを探そうとも見つからないだろうね」
「――――まさか、同姓同名の別人だと言いたいわけではないですよね」
大変癪だが、今更この男が馬鹿げたことを言い出すとは思えなかった。それでも尋ねたのは念のためだ。
「もしそんな結果なら、誠意として僕は君に命を差し出しても構わないよ」
「物騒な言い方は止めて下さい。……違うならいいんです。どちらにせよ、もう彼はほとんどの人の記憶に残っていません。あなたの発言を否定出来るだけの確証がボクには無い」
悪あがきのように反論をぶつけても、どうせまた言い伏せられるだけ。投げやりな心境のまま俯く。答えの分からない問題ばかりが増える現状に、うんざりした気持ちが大きくなっているのも事実だった。
「……なら、自分…………きて……」
ふと、不明瞭でほとんど独り言みたいな小声に気がつく。声の主は言うまでもない。詳しい内容はほとんど聞き取れなかったけれど、ほんの僅かに苦々しそうな気配を感じた。あるいは、何か目論見どおりにいかなかった時のようなものと言ってもいい。ただそもそも、赤司さんには想定外という言葉自体が存在していなさそうだから、多分思い過ごし――
「……全く、手間が掛かる」
――ではなかったらしい。最後の一言は、はっきりと耳に届いた。
「あの、少し聞いてもいいですか」
心の片隅にある気まずさを――偶然とはいえうっかり立ち聞いてしまったので――払拭したくて話題を変える。このひとだけが持つ手札はたくさんあって、意図的に伏せられたままの事実はきっと数えきれない。だったら、そのうちのいくつかを知っておきたいと考えるのは普通のことだと思う。
「言ってみて」
何食わぬ顔で赤司さんは返事をした。彼の呟きの断片をボクが拾ってしまったことは、おそらく見透かされているだろう。でも、本人が追及してこない以上、わざわざ話題に出すつもりはなかった。こういう時は、何事もなかったかのように振舞うのが一番良い。
「黒子くんとあなたはどういう関係なのかなと」
「端的に言えば同居人だ。少し前まで一緒に暮らしていてね」
「えっ、は……? ど、同居!?」
初耳だった。黒子くんが誰かと同じ家で生活していたなんて。何となく、あの物静かな友人はひとりの時間を持ちたいタイプかと思っていたから、驚きで若干声が裏返った気がする。それに赤司さんだって、他人と一緒に住んでいるところを全然想像できない。しかも明日の天気について話しているかのような口調で告げられたから、理解が一瞬追いつかなかった。
「折角だ、いくつか昔話をしようか」
「黒子くんとの……ですか?」
彼はボクの問いかけに答えず、瞳に滲む笑みの色を深くする。切れ上がった涼し気な目じりが、どこか愉快そうに撓んだ。
「あれは存外、我儘な性質なんだよ」
――――意志が強いと言えば聞こえはいい。だが、一度決めると考えを変えることもほとんどない。幸いなことに、結果さえ望んだとおりになれば過程に関しては比較的寛容だが。僕ですら何度も意見を変えさせられたよ。口論になった回数なんて、もはや数えるのが馬鹿らしくなるくらいさ。
「しかも放浪癖まであってね。時々ふらっといなくなってしばらく帰ってこない」
「癖……つまり彼の『家出』は一回や二回のことではないと」
「ああ。最初のころは探し回った時期もあったが、大抵は気が済むと勝手に帰ってくる。だから、いちいち咎めるのも面倒で好きにさせていたんだ」
とはいえ、僕だって同居人が長く不在にすれば一応心配もする。だから何度か迎えに行ってやったこともあるんだけど、そのたびに嫌な顔をされたな。尤も、当の本人は僕にそれを隠せているつもりらしい。目は口ほどに物を言う、なんて教訓も存在するくらいなのに。僕は海のように広い心で見て見ぬふりをしているが、僕以外ならどうなっていたかは分からないな。
本当に愚かで詰めが甘い……時折、内側からは開けられない箱の中にでも閉じ込めてやりたくなるよ。
「こわいこと言わないでくれません?」
「ちょっとした言葉のあやじゃないか。実行しようと思ったことは無いよ。もっと効率の良い方法がいくらでもある」
「ボクが言いたいのはそういう問題では……いえ、いいです。聞きたいわけでもないので。続きをどうぞ」
そう? なら話を戻そうか。君は聡明だから、もうすでに話の結末に見当がついているかもしれないけどね。実のところ、ここ最近は大人しくしていたというか、ふといなくなることはほとんど無くなっていたんだ。理由は分からない。僕もわざわざ話題に出さなかったし、元より然程興味もなかった。
何せ、どれだけ姿をくらませても、最後には必ず帰ってくると知っていたから。それだけ分かっていれば十分だろう?
「帰巣本能みたいなものでしょうか」
「さてね。あれが真実何を考えているのかなんて、僕には分からないよ。知りたいとも思わない。どうせ考えが食い違っておしまいだ」
「なんというか、ボクが知ってる彼とはずいぶん違う……」
他者に見せる『顔』は、あらゆる側面のうちのひとつに過ぎないものさ。きっと、当たり障りのない人物像を演じていたんだろう。君の知る『黒子テツヤ』は――――そうだな、おそらく物静かで自分の意見を強く主張することもない、気が付くとどこかで小説を読んでいるような、影の薄い落ち着いた子という印象だったんじゃないか。
「見てきたように言うんですね。まあ、実際そのとおりなんですけど」
「単なる経験則だよ。確か、あまり興味を持たれたり詮索されることがないから楽だと言っていた覚えがある」
「……あなたと黒子くんが同居していたという話に、ようやく実感が湧いてきました」
まるで僕を信用していないように聞こえるな。言っておくが、僕は嘘が嫌いだしつまらない冗談も言わないよ。まあいい、無駄話を続けても仕方ないからな。
気が済んだのか飽きたのか、あるいは別の理由なのか、とにかく暫くの間僕の手を煩わせる要因がひとつ減ったのは確かだ。尤も、これはあくまで一時的なことだったが。ある日何の前触れもなく、普段と変わらない様子で出かけたと思ったらまた戻ってこなくなった。
「それから今日に至って、あなたは彼を探しに来た、というわけですか?」
「おおよそは。出来れば僕の手を煩わせないでほしかったんだけどね」
ただもう少し正確を期すなら、探しにではなく迎えに来たと答えるべきかな。
「迎え……? だけど彼は」
「おや。まだ気づいていないのかい。もうとっくに見つけているよ」
――――『頃合い』だ、と彼は告げた。
「君は今、無視できない疑問をいくつか抱えているだろう? それも黒子テツヤにではなく、僕に対して、だ」
「……何の話ですか」
咄嗟に否定も肯定もしない曖昧な返事を選ぶ。赤司さんの問いかけは半分正解で、しかし半分は間違いだった。なぜなら、当初頭の中にあったはずの強い違和感や不信感は、彼と向き合って話しているうちにいつの間にか消えていたからだ。奇妙な状況と正体不明の男への本能的な警戒心が、ほとんど失われていることを認識した瞬間、愕然とした。
しかも、その事実を自覚したのはほんのついさっきだった。淡々と言い放たれた『頃合い』という言葉を耳にした時、輪郭すら曖昧になった危機感が不意に呼び起こされたのだ。もしかすると、あの一言が引き金になったのかもしれない。確証はないけれど、こういう時の直感は侮れないと知っている。
でもそれは同時に、ボク自身の思考そのものが、何らかの原因であやふやなかたちに変えられてしまったという証明でもあった。
どれほど非現実的な推測なのかは自分でも分かっている。でもありえない選択肢をひとつずつ除外して、最後に残った可能性が唯一なら、それを答えとするほかない。そんな行動を実際に起こせる人物の心当たりもひとりしかいなかった。だから軽はずみな言動は出来る限り避けて、今は相手の出方を窺う必要がある。
「はは、そう言うと思った。僕の目的が……真意が何なのか、少しでも把握したい、というところか」
宝石みたいに鮮やかな双色の瞳は、深淵のように底知れない。一度見たら忘れられなさそうな美貌の中でも、特に際立って視線が吸い寄せられる。
「しかし先ほども言ったはずだ。僕は嘘が嫌いだとね」
手持無沙汰にテーブルへ置かれていたボクの手を、赤司さんが掴んだ。拳全体を覆うように手首を捕らえる彼の掌は思いのほか大きい。身長はあまり変わらないのに、と妙に他人事めいた不満が頭をよぎる――――直後、赤司さんはボクを引き寄せた。
「わっ……!?」
そのまま流れるように身を乗り出すと、お互いを隔てるテーブルに軽くぶつかった。突然の振る舞いに驚いて、どう反応すべきか考えが及ぶよりも先に、ただ元凶の男を見つめる。
「僕がここにいる理由はひとつしかない。黒子テツヤを探している、ただそれだけさ」
最初にそう話しただろう、と。彼は同じように身体を傾けてこちらへ顔を近づけた。けぶるような長い睫毛がはっきりと視認出来る。対になった深紅と黄金の虹彩を、息がかかるほどの近さで捉えた。
「ずっと君を探していたんだ」
――――テツヤ。
びっくりするくらい優しく甘い声が聞こえて、爪先まで整った長い指がボクの顎をすくい上げる。自分の意思で身体が動かせないのは、赤司さんに手を掴まれているせいなのか、それとも他に理由があるのかは分からなかった。けれど、ひとつだけ確実に断言出来ることがある。
「ボクは黒子テツヤではありません。これ以上ふざけたことを言うなら、帰ります」
「いいや、お前だよ。僕がテツヤを間違えるわけがない」
冗談にしても性質が悪いです、と言いかけて口を噤んだ。危ない。このひとは間違いなく同じ話を何度もしたがらないタイプだ。つまらない冗談は言わないと確かに話していたから、今は変に機嫌を損ねさせたくなかった。何せ赤司さんとの距離が近すぎて、物理的な手段に出られたらほとんど抵抗する術がない。
「信じられないという顔をしているね。目は口ほどに物を言う……僕には隠せないよ」
「むしろこの状況で、あなたの言葉を信じるほうが難しいと思いますが」
「そう? なら、興味深い話をひとつしてあげようか」
まばたきの気配さえ感じそうなすぐそばで、目蓋が笑みの影を宿した。輪郭に触れていた手は、首筋を伝い肩へと下りていく。そのまま、力を込めずに軽く押された。すると不思議なことに、全く動かなかったはずの四肢はあっけなく脱力して元の席に収まる。状況を理解するほんの数秒のうちに、真正面の男も同じく腰を下ろしていた。
「かつて僕に、上手く『擬態』するために何が一番必要だと思うか、尋ねてきた奴がいた」
曰く、知識か経験か。もしくは他に重視すべきものがあるのか、と。
「……あなたは何て答えたんです?」
「考えるまでもないな」
彼はまるで昨日のことのように口を開く。
「――――『忘却』だ、と言ったのさ」
忘却。忘れること。思い出せなくなること。あまり良い意味で使われることのない単語だ。それが擬態という言葉とどう繋がるのか、すぐには結びつかなかった。
「何故僕がそう答えたのか、知りたい?」
「心を読まないでください。……キミは、嘘が嫌いなんでしたっけ」
一瞬、赤司さんはおや、と目を瞠ったような表情を滲ませた。でも本当にごくわずかな変化だったから、見間違いかもしれない。自分の錯覚を疑いながら、相手の言葉をじっと待つ。
「ああ。よく分かっているじゃないか」
どこか満足げな声が返された。
「元の記憶がある限り、些細な癖や習慣は意識せずとも表に出てきてしまうものだ。たとえ自分が隠しきっているつもりでもね。だが、いっそ全て忘れて『別の誰か』になってしまえば、下手な言い訳や誤魔化しも必要なくなる」
ここまで聞けば、さすがに彼の言いたいことは察せられた。おそらく、黒子テツヤが『別の誰か』になってしまった結果がボク……という話なのだろう。内容の真偽はひとまず置くとして、理屈自体は分からなくもない。けれど、それを認めるには立ちはだかる大きな――しかも実現が限りなく不可能に近い――問題を超える必要がある。
「意図的に忘れる、なんて普通は出来ませんよ。しかもそのうえで、別の黒子テツヤを存在させるなんて」
「少し視点を変えてみればいい。そもそも、『君の友人』を誰も覚えていないんだろう? ならばこんなふうに考えることも出来るわけだ」
最初から、そんな人間は存在しないのだと。
「お前自身が黒子テツヤではない、というちょっとした根拠のようなものだな。初歩的な暗示に近いが、効果はそれなりに期待出来る」
「だから、前提からしておかしいんですよ……! ボクがそんな、現実離れしたことを出来るわけがないでしょう!?」
ほとんど睨むように赤司さんへ視線を向けた。温度の欠けた双眸が、静かにこちらを見返す。……駄目だ、落ち着かなければ。まくし立てようとした自分を制して、唇を噛み締める。――――そしてふと気がついた。彼の目を見ていると、逆立ったはずの感情や疑問が驚くほどあっさりと静まっていくことに。
「……ほう。気がついた?」
当たり前みたいに思考を読んでくる発言は、もう気にしないほうがいいかもしれない。いや、本当は気にしないでいられるはずもないのだけれど。テーブルに軽く頬杖をついて、返事を待つ赤司さんの姿はとても絵になっていた。こんな状況でなければ素直に褒めていただろう。とはいえ、口を開けば難しいことばかり言うという印象は変わらない。
「あなたが『変なひと』だっていうことになら、とっくに気がついてますが」
「強がっているのかな? かわいいね」
言うが早いか、彼は眉をぴくりと動かして舌打ちでもしそうな表情を浮かべた。
「……は? 何なんですか、急に」
最初から余裕を崩さないところばかり見ていたせいか、なんだか珍しいものを目にしたような感覚に襲われる。どうしたんだろう。内心で首を傾げた時、彼の綺麗な指先がこつんと一度テーブルを叩いた。その仕草には、かすかな苛立ちが滲んでいるようにも思えた。
「いや――――ただの、たわごとだ」
そんなことよりも、と赤司さんは素知らぬ顔で続ける。ほんの一瞬、妙な流れになりかけた話はすぐうやむやにされた。どうして彼があんなことを口走ったのか、わずかに興味と好奇心が疼く。でも、それらが芽吹く前に蓋をした。
「僕の目は何色に見える?」
「もう、やっぱり急じゃないですか……右目が赤で、左目が金や琥珀のような色に見えますが」
「素直に言ったね。お前の答えは正しいよ」
こつん。もう一度、彼の指先がテーブルを叩く。今度は先ほどのように不愉快そうな雰囲気が一切無く、獲物を嬲る直前の猫みたいに、唇の端が意地悪く吊り上がっていた。お世辞にも良い表情だとは言えなくて、背筋がわずかに粟立つ。
「だが、お前以外の人間は違う答えを口にするだろう。僕の目は赤でも金でもなく、どちらも黒いと」
ありえませんとか、まさかとか。反射的に否定の言葉を言いかけて、ふと口を噤んだ。
そういえば、最初にこのひとの存在を知らせてくれた友人はどういうふうに話していたっけ。確か――――男で、赤い髪で、びっくりするくらい顔が綺麗。今にして思えば、相当分かりやすい『特徴』については一言も触れていなかった気がする。もちろんただの偶然かもしれない。けれどどちらにせよ証明する術は無く、ボク自身は出会った直後に自然と赤司さんのオッドアイに視線が吸い寄せられた。それだけは確かだ。
「僕の正しいかたちを認識できる、だからこそお前が黒子テツヤなんだよ。取るに足らない人間には成し得ないことだ」
こつん。再び軽い音。
「取るに足らないって、まるで自分が違ういきものみたいに言いますね」
「否定はしない。改めて言う必要もないとは思うが、僕は嘘が嫌いなんだ」
「……キミの話には客観性がありません」
赤司征十郎と名乗った男が、凡庸な器に収まるような人物でないことは――少々悔しくあるものの――もちろん理解している。でも先ほどの発言が比喩でもなんでもなく、人間という生き物の境界を越える話であれば、すぐに頷くのはさすがに難しい。尤も、心のどこかではとっくに答えが出ているのだけれど。
「なるほど。お前の中の『常識』が認めることを邪魔しているわけか。やはり人なんて面倒なだけだな」
「まだ何も言ってませんってば」
「お前の考えていることくらい、すぐに分かるよ。それとも、わざわざ声に出されないと納得出来ない?」
こつん。心なしか、音が遠くなったように感じた。
「大体、お前自身だって僕と似たような状態じゃないか。せっかく唯一無二の色を持っているのに」
「似たような……? つまり、ボクの目が赤か金ってことですか?」
この問いかけを肯定されたら、即座に反論するつもりだった。だって鏡を見れば分かることだ。そこに写るのは、何の個性も無い平凡な大学生の姿だけ。今日だって同じだった。元々存在感が薄く、大勢に埋没して過ごしているボクに、他人の目を惹く鮮やかな特徴が備わっているわけがない。
「いいや、違う。本来なら、僕よりもテツヤが持つ色のほうがずっと美しい。だが、人の目は僕たちの正しいかたちを捉えられない。きっと都合よく、理解が及ぶ姿にすり替わって見えているだけさ」
――――何せ、お前は『擬態』するためだけに僕のことさえ忘れてしまったのだから。
こつん。さっきよりもかすかに小さくなった音は、かろうじてボクの耳に届いた。視界の端にあるはずの見慣れた店内は、まるでモノクロの写真みたいに輪郭が曖昧で、どこか遠い気がする。彼から目を逸らして確認すれば良いと分かってはいても、何故か身体はびくとも動かなかった。
「正直、こういう回りくどい方法は僕としても避けたいんだけどね。残念ながら、何事にも例外というものは付き纏う」
「そんなこと言って、ずっとキミは、言葉も行動も回りくどい、じゃないです、か」
唇が徐々に重くなってくる。ちゃんと返事出来ているのか判断がつかないくらい、口の動きが鈍い自覚だけはあった。
「うん、悪くない。だがこんな簡単なものも防げないんだな。確かにこの有様なら、もう少し早く迎えに来ても良かったか」
柘榴と、それから煮詰めた蜂蜜の色を持つふたつの瞳がわずかに細められる。視界の先の双眸は暗くもないのに鈍く光って、不気味に思うより先につい見惚れてしまった。その間にも、眠くて仕方ない時のような抗えない感覚に意識が遠のく。
「あいつの言葉を借りるわけではないが、待つのにも些か飽いていたんだ。僕はお前のために存在しているのに、肝心の『主人』がいないのでは味気ないと思わないか」
あいつ? ボクのため? それに……主人? 聞き返したいことはいくつもあったけれど、声を出すことは出来なかった。そのまま上半身の力が抜けていく。テーブルに頭をぶつけるかも、と悪あがきのように一瞬だけ冷静になりながら、諦め半分で考える。でも完全に倒れ伏すよりも早く、どこか懐かしい温かな感触に包まれた。
「なに、すぐに思い出さずとも構わないよ。僕たちにとって、時間は果ての無いものだ」
その声の終わりに、何が変わってしまうのか。ボクにはもう分からなかった。
「……ん? あの人ってこないだの」
大学から歩いてすぐに行ける距離にあるマジバは、手軽さを重視するなら圧倒的な強さを持つ。だから早朝とか深夜、それと休みの日以外は大概混んでるし、知ってる顔に偶然会うことも珍しいことではなかった。でもちょっと予想外というか、ついこの間、一言二言話しただけの相手を『知ってる顔』に分類していいのかは微妙なところだ。
「にしても、こういうとこ似合わなさ過ぎだろ」
鮮明な赤い髪ってだけでも目立つのに――染めているにしては綺麗に色が入りすぎだと思う――確か、顔もめちゃくちゃ良かった。少なくとも俺は、一度見ただけなのに今も覚えている。他人の外見なり名前なりに関する記憶力は結構個人差が出やすいけど、ここまで抜きん出た美形ともなれば、すぐ忘れるほうが難しいだろう。
実際、その男は周囲の視線を一心に集めていた。言うまでもないが、特に女子からの熱い視線が大変分かりやすい。当然ながら、恐ろしく『注目』を集める場所に自分から飛び込む気は一切起きず、少し離れた場所に座ろうと考える。ついでに空いている席を探すべく辺りを見回した。まさにその時だ。
「やあ、こんにちは」
「ぅお!?」
思いのほか近くから声がして、心臓が一瞬止まったかと思った。まだバクバクしたまま、元凶たる人物の方へ振り返る。
「こ、コンニチハ」
若干棒読みになってしまったのは見逃してくれ。
まず目に付いたのが深紅の髪で、次にどこの王子様だよって言いたくなるよく出来た顔立ち。身長は俺より低いけど、タッパが無いわけじゃない。百八十には届いてないかもな、くらい。つまり何が言いたいかって、知らないふりをしたかった例の人にばっちり見つかったってわけだ。
「良かった、人違いだったらどうしようかと思っていたんだ」
「えーと……俺を探してた、んですか」
「そう。お礼が言いたくてね。何日か前に、そこの大学で声を掛けたことがあっただろう」
人を探している――――あの時、開口一番に告げられた内容だった。もちろん覚えていますとも。今みたいに高そうなスーツで大学の敷地内を歩いてたから、スゲー浮いてたし。誰かの知り合いか? なんて、呑気に眺めてたんだよな。途中までは。
「君のおかげで、無事に目的を果たせたよ」
「そう、なんすか。だったら良かった。あんま大したことはしてない気はしますけども」
俺が話したことなんて、精々尋ねられた名前の奴を知ってるかどうかくらいだったはず。たったそれだけで何が分かるんだよって感じだけど、意味があったなら悪い気はしない。まあ、生徒数の多い大学だから、多少なりとも手掛かりにはなったんだろう。確かそいつの名前は――
「ああ、覚えてなくとも無理はない。たった一回聞いただけの名前なんて、普通はすぐ忘れてしまうものさ」
――ハイ、仰るとおりで。
「あー……っと、他に何かある、っすか?」
「最後にひとつだけいいかな」
声音を聞いただけで分かる。これはあれだ。一見伺ってるようで、実は返事を求められていないやつ。多分もう決定事項。高校にいたわ、こういうタイプの先輩。目を細めるような、笑ってるのに笑ってない表情までそっくりだった。いや、さすがにここまで見た目は整ってなかったけど。
「次に声を発した時、君は『日常』に戻っている。忘れたことを忘れ、思い出せないことは無いものになるんだ」
「……え?」
赤い目だ、と認識した瞬間、ぷつんと電源が落ちたように思考が止まる。
「全く。オレだって早く……たいのに、たまには…………だなんて面倒……言い……なんて」
夢うつつに耳まで届いた不満そうな言葉は、まばたき一回分の時間が過ぎた後、全部泡のように消えてしまった。わずかな立ちくらみに似た浮遊感をやりすごして、何回かゆっくりと呼吸をする。
「疲れてんのかな。一瞬ぼーっとしてたし、とりあえずどっか座るか」
いつもどおり変わり映えしない店内を見渡して、空いている席を探した。どうやら今日は、知ってる奴は誰もいないみたいだ。
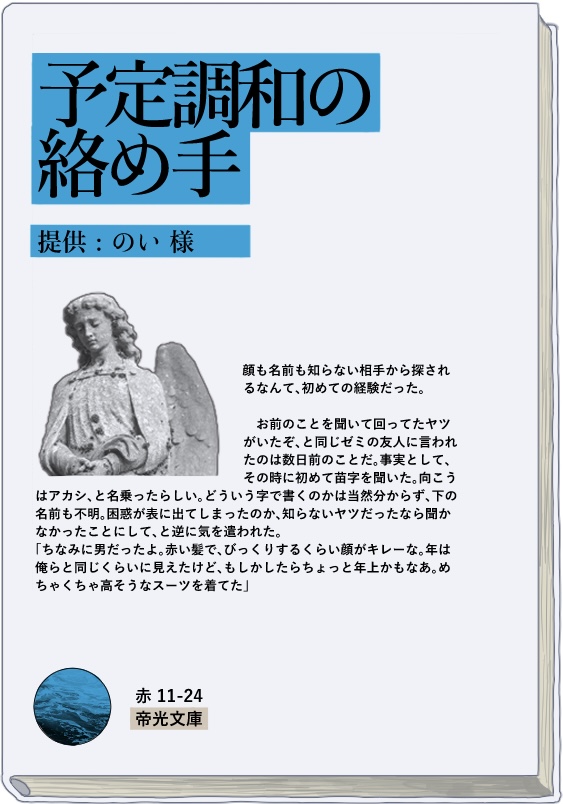
「予定調和の絡め手」
提供 : のい様
